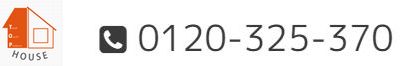室内仕上げ材

壁・天井材① クロス<住まい手による日常のお手入れ>
日頃から、はたきなどで埃を落とします。ビニルクロスは、よく絞った布などで水拭きや中性洗剤で拭き掃除をします。剥がれがあれば、クロス用ボンドで補修します。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
経年劣化により、クロスが縮んだり、下地が湿気や乾燥で伸縮することで、クロスの継ぎ目が開き隙間が生じます。放置すると広がるので、住まい手がお手入れすることで被害を小さくできます。ビニルクロスにカビが付着したままでは衛生的に好ましくなく、アレルギーや喘息などの病気を招く恐れがあります。
<メンテナンススケジュール>
一般的にビニルクロスの寿命は20年といわれており、20年毎に張替えが必要です。
<材料・注意事項・トラブル防止・その他>
劣化した部分だけではなく、一部屋単位、1階2階などの階単位、家全体、などで張り替えることが望ましい。一見してあまり劣化していない部分でも、古い部分と新しく張り替えた部分が隣合わせで見ると、見た目に違いが出ます。ビニルクロスを張り替える時は、下地も同時にチェックします。ビニルクロスがカビている部分は湿気がたまりやすく、ボード自体もカビが発生している可能性があります。
壁・天井材② 塗り壁<住まい手による日常のお手入れ>
表面のほこりが気になる場合、はたきなどで落とします。手垢などの汚れは固く絞った雑巾やスポンジで叩き洗いをします。表面の汚れが気になる場合、可能な仕上げならば消しゴムやサンドペーパーなどで落とします。酷い汚れは中性洗剤、漂白剤を水で薄めて布やスポンジで叩き洗いをします。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
塗り壁材により、接着剤の劣化による仕上げ材の粉吹きや剥がれが見られるようになります。地震等の振動、木材の収縮等によるクラックが生じる場合があります。
<メンテナンススケジュール>
20年を目安に塗り替えをします。
<材料・注意事項・トラブル防止・その他>
清掃に薬剤等を使用する場合は目立たないところで試してから行います。雨漏りによる跡がある場合は、塗り替えだけでなく、雨漏りの原因を見つけ根本治癒が必要です。塗り壁は乾燥により収縮し、隙間が開く場合があります。
壁・天井材③ 板張り<住まい手による日常のお手入れ>
表面の埃が気になる場合、ハタキなどで落とします。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
雨漏りが原因で起こるシミをそのまま放置しておくと、躯体にまで劣化が広がるので早めに確認をします。
<メンテナンススケジュール>
板張りは、基本的にはメンテナンスは必要ありません。
<材料・注意事項・トラブル防止・その他>
雨漏りによる跡がある場合は、張替えだけでなく、雨漏りの原因を見つけ根本治癒をしましょう。
床材① 複合フローリング<住まい手による日常のお手入れ>
日常は乾拭きをします。半年~1年に1回ワックスかけをします。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
窓の近くの直射日光が当るところは、表面が劣化しやすく、塗装が剥がれたりひび割れが発生しやすくなります。放っておくとフローリング全体にひび割れが進行します。家具などにより部分的に剥がれてしまうことがあります。
<メンテナンススケジュール>
25年ごとに張替えをします。
<材料・注意事項・トラブル防止・その他>
床面がたわむ原因は、床構造がたわんでいる場合と、床構造には問題なく床材の基材合板の劣化によってたわむ場合とがあります。
床材ー②無垢フローリング/塗膜系塗料
<住まい手による日常のお手入れ>
毎日のお手入れで、掃除機で塵やゴミを取り除きます。水気は無垢材を傷める原因になります。表面の汚れが気になる場合には、乾いた布で乾拭きを行ってください。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
表面を膜で覆っているので、汚れは比較的つきにくいです。ワックスは基本的には必要はありません。どうしても水拭きが必要な場合は、硬く絞った布で表面を拭きあげて水気が残らないように拭きとってください。
<メンテナンススケジュール>
無垢フローリングの塗膜系塗料仕上げ材は30年目にサンディングの上、塗装します。
<材料・注意事項・トラブル防止・その他>
艶出しを目的としたワックス等の使用は、製品特性をよく確認した上でご使用ください。ワックス使用時、または通常清掃時等で水分を使用する場合は、水気をしっかりと拭きとってください。無垢フローリングは湿度によって収縮するので隙間が生じることがありますが、数年でおさまります。
床材③ 浸透系塗料<住まい手による日常のお手入れ>
表面の塵やゴミを掃除機で取り除きます。必要であれば乾いた布で乾拭きしてください。ただし、水拭きは表面の塗料が取れてしまうので厳禁です。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
必ずメンテナンスをしないと無垢材を傷めるものではありませんが、頻繁な歩行などで自然塗料が摩耗する場合はワックスかがけをします。定期的に塗装することにより、無垢床材内部まで浸透して保護力が上がり、無垢床材本来の色やツヤも増します。
<メンテナンススケジュール>
10年毎のオイル塗装で表面の保護をし、30年をめどにサンディングの上、塗装をします。塗装面積が広い場合、日焼け面との仕上げムラをなくすためにサンディングを行い、下地の無垢材を研磨して自然塗料を施すと、全体の色むらがなく自然な仕上がりとなります。
<材料・注意事項・トラブル防止・その他>
塗装されたオイルと同じメーカーのワックスをかけることを推奨します。部分的な再塗装であれば、乾いた布に自然塗料等を付着させ、再塗装を行ってください。試し塗り用の小さなを購入し試し塗り後に塗装用を購入することをお勧めします。一般的なフロアーワックスはご使用できません。樹脂ワックス、水性ワック共に不可です。無垢フローリングは、湿度によって収縮するので隙間が生じることがありますが、数年でおさまります。
床材④ 塩ビ系塗料<住まい手による日常のお手入れ>
掃除機で塵やゴミを取り除き、固く絞った布巾で拭きます。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
剥がれを放置しておくと、剥がれがだんだん広がるので、早めにメンテナンスをします。
<メンテナンススケジュール>
一般的に塩ビ床材の寿命は15年程度です。15年ごとに張替えをします。剥がれなど目立った劣化がある場合にも張替えをします。
床材⑤ 畳<住まい手による日常のお手入れ>
日々きつく絞った布で拭くか、畳の目に沿って掃除機で掃除をします。年に2回程度、晴れた日に日干しで乾燥させます。畳の上に絨毯やカーペットの重ね敷きはおすすめしません。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
3~5年すると、畳表が日に焼けて変色したり、擦り切れたりするので、畳の裏返しをします。
<メンテナンススケジュール>
5年毎に裏返しと表替えを繰り返し、30年を目処に畳替えを行います。畳がへたってきたり、踏んだ時にへこむような感覚があったり、畳に大きな隙間ができたりした場合は新しい畳に交換します。
床材⑥ タイル・石<住まい手による日常のお手入れ>
場所により汚れ方やお手入れの方法が異なります。居室の床は掃除機等でほこりを取り除きます。玄関のタイルなどはデッキブラシやモップ掛けをし、布で水拭きします。トイレはトイレ用の洗剤で掃除します。浴室は浴室用の中性洗剤を使用します。キッチン周りのタイルは中性洗剤で油汚れを落とします。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
汚れを放置すると、そのままシミになることがあります。タイル表面や目地に割れがあると隙間からゴミや水分が入り込んでしまうので、目地埋め補修を行ってください。
<メンテナンススケジュール>
10年目に目地補修を行い、その後10年毎に点検し、必要があれば補修をします。
<材料・注意事項・トラブル防止・その他>
塩素系洗剤と酸性洗剤を同時に使用しないようにします。水洗いをした場合は汚染水はきれいに拭き取ります。
床材⑦ カーペット<住まい手による日常のお手入れ>
カーペットの汚れの80%は浮遊しているほこりです。3日に1度は掃除機でゴミ・ほこりを取り除きます。掃除機は逆目にかけます。液体をこぼした場合は決してこすらずに叩くようにして汚れを取り除きます。天然ウールの絨毯は、初めのうちは遊び毛が出てきますが、日常の掃除機がけで少しずつ減っていきます。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
定期的な掃除を怠ると、ほこりが溜まるだけでなく、汚れが蓄積し取れにくくなり、ダニやニオイの発生につながります。
<メンテナンススケジュール>
20年目毎に張替えをします。
<材料・注意事項・トラブル防止・その他>
ウール100%のカーペットは、毛が抜けることはありません。抜けたように見える毛は「遊び毛」といって本体の毛ではなく余分な毛です。家具の凹みは、ぬるま湯で湿らせた布で水分を与えたあと、ドライヤーを使ってブラッシングすることで元に戻ります。粘着クリーナーは表面のくずやほこりを取るだけで、カーペット内部にゴミやほこりを残すことになるのでおすすめしません。カーペットのつなぎ目が見えることがあります。
建具① 新建材系建具<住まい手による日常のお手入れ>
乾拭きで本体や丁番部分のほこりを落とします。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
丁番ネジのゆがみにより、戸が傾く、ドアが閉まらないなどの症状が出てきます。扉が枠にこすれたり、周囲の化粧材を傷つけたり、扉が脱落する危険性もあります。表面材が剥がれてくることがあります。
<メンテナンススケジュール>
1年後に点検・調整を行います。30年後に点検をし、必要に応じて補修をします。
<材料・注意事項・トラブル防止・その他>
竣工後、冬など乾燥時期のがたつき、梅雨時期の膨らみで建具の動きは変わるので、1年後の点検で確認します。
建具② 製作建具<住まい手による日常のお手入れ>
週に1回程度拭き掃除を行います。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
丁番ネジのゆがみにより、戸が傾く、ドアが閉まらないなどの症状が出てきます。扉が枠にこすれたり、周囲の化粧材を傷つけたり、扉が脱落する危険性もあります。表面材が剥がれてくることがあります。破損や襖紙の破れがある場合は補修します。
<メンテナンススケジュール>
1年後に、点検・調整を行います。30年後に点検をし、必要に応じて補修をします。
<材料・注意事項・トラブル防止・その他>
竣工後、冬など乾燥時期のガタつき、梅雨時期の膨らみで建具の動きは変わるので、1年後の点検で確認します。
建具③ 建具金物<住まい手による日常のお手入れ>
可動金具部分の動きが悪い場合、シリコンスプレーで動きを良くします。鍵穴にはパウダースプレーを使用します。Vレールの溝にはゴミが落ちやすいのでこまめに掃除をします。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
レバーハンドルのバネが戻らなくなることがあります。戸車の劣化により、ドアの開閉の動きが悪くなります。ラッチ、ハンドルは錠本体が破損したり、ドアが開かなくなる可能性があります。戸車やレール部分の劣化により、引戸が最後まで閉まらなくなったり、動きが悪くなることがあります。
<メンテナンススケジュール>
10年目から5年毎に点検をし、必要があれば補修をします。
建具④ 造作材<住まい手による日常のお手入れ>
定期的に乾拭きをします。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
日当たりの良い場所やストーブの周辺などでは、木材の表面が急激に乾燥するため、表面にひびが発生することがあります。ささくれだってきます。
<メンテナンススケジュール>
新建材系の造作材は、10年目ごとに点検をし、必要であれば補修をします。無垢系の造作材は、10年目から5年毎に点検をし、必要があれば補修をします。
建具⑤ 造付家具<住まい手による日常のお手入れ>
定期的に乾拭きをします。
<メンテナンスサイン・放置するとおこる現象>
木口のシールが剥がれてくることがあります。放置しておくとだんだん広がりますので、早めにメンテナンスをします。扉が傾いたりズレたりしたら、丁番の調整が必要です。放置しておくと丁番も損傷してしまう場合があり、扉の落下の可能性もあります。
<メンテナンススケジュール>
新建材系の家具は10年毎に点検をし、必要であれば補修します。製作家具は10年目に点検、その後5年毎に点検します。